個人事業主として業務委託する方に向けて、軽貨物ドライバーの税金事情について解説していこうと思います。
はじめての業務委託契約、納税体系がサラリーマン時代とは大きく異なり、思わぬところで出費が出てしまうものです。
税金の種類も所得に応じて増えていきますから、事業を行う前に税金が年間どのくらいかかるのかを知っておかないと、後々困ることになっちゃいます。
 クロ
クロ税金こんなにあったのか、会社員の時はあまり深く考えることはなかったけど会社は守ってくれていた…
今回は、個人事業主の納税事情について詳しく解説していきますよ!!
はじめに… 給与所得控除と経費の違い


サラリーマン時代なら税金関係は全て会社に任せておけば大丈夫でしたね!!
けど、個人事業主になると自ら納税に行くことになります。
会社員の時とは違って、「年収」の定義がすこし変わってくることも理解しておかねばなりません。
☑ 給与収入-所得控除 = 給与所得
会社員でいう年収というのは、一般的に「給与収入」を指します。
そこから所得控除を差し引いたものが、いわゆる給与所得になります。
所得控除には色々ありますが、給与をもらっている人には「給与所得控除」と言われる強力な控除が付きます。
世の中で言われる「103万円の壁」とは、この給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足したもので、103万円以下ならば所得税がかからないという領域です。
給与所得控除額は以下の通り。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
会社員であれば、この定められた金額分が控除されていました。
個人事業主になると、「給与所得」 ⇒ 「事業所得」に切り替わります。
☑ 売上ー必要経費ー所得控除 = 事業所得
「経費」というのは事業をするのに必要な物・金・人件費などをそのまま控除額に適応させことのできる非常に都合の良い項目です。(例:車、自宅兼事務所、パソコン、カメラ、会食、会食費など、事業に関係するならその購入額が全額or一部、そのまま控除額になる)
サラリーマンの場合は、国によって「給与所得控除」を一方的に決められており、経費という概念を持てず、所得を下げるという節税対策が困難でした。
車買おうが、パソコン買おうが、それは実費からで、「個人事業主なら経費にできる項目」が単なる娯楽品としての扱いにしかならない、結果として税金を余分に支払うようになっていました。



サラリーマンの時は税金に対する考え方が甘かったんだよね…
個人事業主の場合は、この経費枠をうまく利用することによって、累進課税額を調整することができ、節税によって利益を確保しやすくなります。
サラリーマンにとっての年収は、「給与収入」。
個人事業主にとっての年収は、「利益」となります。
※所得控除は多岐にわたる!!
(雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険控除・地震保険控除・寄付金控除・障害者控除・ひとり親控除・勤労学生控除・扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除など…)
個人事業主が納める税金は「租税公課」と「事業主貸」


個人事業主が納める税金は「租税公課」と「事業主貸」の2種類です!!
この2種は非常に重要で、「経費にできるもの」を分ける区分となっています。
事業に対してかかる税金、勿論経費になります。
(個人事業税・消費税・固定資産税・不動産取得税・自動車税・登録免許税・印紙税・会費や組合費等)
個人に対してかかる税金、一国民としての義務なので経費にはなりません。
(所得税・相続税・住民税・罰金(国税や地方税の延滞金、交通違反等)
租税公課は事業に関係したものにかかり、事業主貸は利益に対してかかるものです。
利益を多く残せば、事業主貸も膨れ上がります。
これから先は、軽貨物ドライバーに直接関係する7つ税金について、詳しく解説していきます!!
所得税


1年間(1/1~12/31)に得た所得にかかる税金です。
納税者は原則2月16~3月15日の1ヶ月の間に、全体売上から経費を差し引いた「所得額」を国に報告する義務があります。
これを「確定申告」と言います。
その確定申告をもとに算出された所得には「超過累進課税方式」が適応され、個人の所得額に応じて5~45%の税金を課されることになります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 ~ 1,949,999円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 ~ 3,299,999円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 ~ 6,949,999円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 ~ 8,999,999円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 ~ 17,999,999円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 ~ 39,999,999円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
この超過累進課税方式には「速算表」と言われる課税額を簡易的に表しているものがあります。
非常に便利なツールであらかじめ決められた控除額を引くことで、簡単に大まかな所得が割り出せてしまいます!!
例えば、年収350万円の人がいたとするならば、この表によるとその人の負担額はこちら✋
3,500,000×20% - 427,500 = 約27万円
単純に年収350万円に20%かけて、そこから控除額を差し引くと所得が算出します。
ただ、気をつけなければいけないことが一点あります、この速算表は「誤解を生みやすい表記」であり、本来の超過累進課税率の意味とは異なるという点です。



ほんま紛らわしい表記なのよ
本来の所得計算は、階層に応じて税率をかけていくんです。
先ほどの350万円を例にすると、5%がかかる範囲、10%がかかる範囲、20%がかかる範囲あり、この3つの範囲の合計より所得税が算出される仕組みになります。
つまり、正しい計算方法は以下のとおり!!
(1,949,999円×5%)+(1,350,000×10%)+(200,001×20%)= 約27万円
350万円のうち
¥1~¥1,949,999 の範囲までは5%
¥1,950,000円 ~ ¥3,299,999円 の範囲までは10% (¥1,349,999分は10%がかかる)
¥3,300,000円 ~ ¥6,949,999円 の範囲までは20% (残り¥200,000分は20%がかかる)
年収350万円だから、「3,300,000円 ~ 6,949,999円の20%をそのままかけちゃえ!!」はダメなんですよね。
意味合いがまるで違います!!
速算表は控除額を差し引くことで簡易的に所得計算ができるようになっていますが、本来の意味合いは区分ごとの合算値ですので、そこを忘れないようにうまく活用していきましょう。
住民税


住民税は「都道府県民税」と「市町村民税」からなり、一括もしくは4回に分けて6・8・10・1月に納付します。
計算方法は「均等割」と「所得割」の合算によるものです。
納税者の所得に関わらず均等に徴収される、通常は市民税3000円、県民税1500円だが、地方によって徴収額が変わることもある。
( 例:広島県広島市、 市民税:3500円 県民税:2000円 、復興特別税を含む)
■(所得金額-所得控除)×税率-控除額
前年度の所得により課税額が変動する。
※控除項目や控除額はお住まいの市区町村によって変わります、基本的な税率は県民税4%、市民税6%です。
納税地は1月1日時点のお住まいになります、年内に引っ越した場合は翌年からその地域での納税です!!
復興特別税


2011年3月11日に、東日本大震災が発生しました。
その復興資金として、国民には特別税として課税が義務付けられています。
所得税と住民税から徴収されることになります。
期間は平成25年~令和19年、「所得税額×2.1%」を併せて申告・納付。
期間は平成19年~令和3年、市民税500円、県民税500円、あわせて1000円の加算。
住民税部門は令和3年に終了していますが、なんかお国さんは「森林環境税」とかいうのを新たに作って同額1000円の強制徴収をしています、なので実質終わっていません…(笑)
消費税
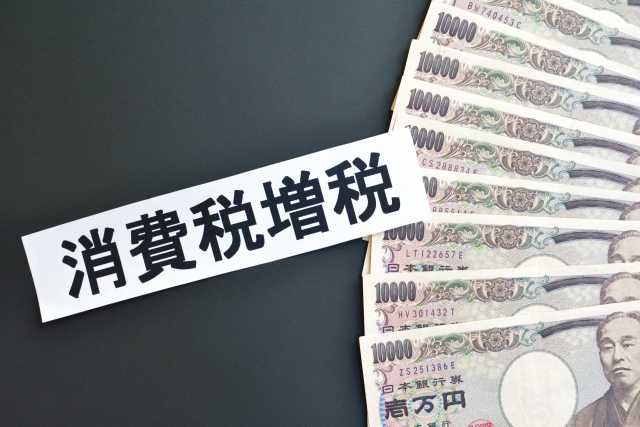
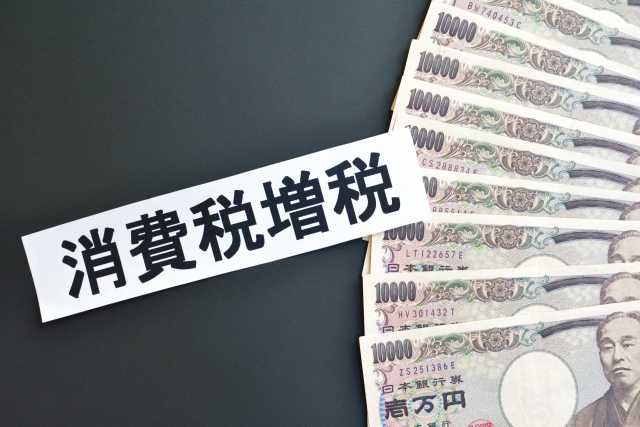
税金には「直接税」と「間接税」2つの区分があり、消費税は間接税に分類されます。
「税を負担する人」と「税を納める人」が異なる税金のことで、事業主は一時的に消費税を保管する立場になります。
保管した消費税は確定申告の際に、国へ支払う義務があり、それを忘れていると思わぬ出費になってしまうわけです。
ですが、この消費税には、実は免税措置があるんです。
そのボーダーラインは売上1000万円!!
売上が1000万円以上の方は課税事業者として消費税10%の支払い義務が発生し、2年後から支払いを求められます。
逆に、売上が1000万円ない方は免税事業者となり、消費税の支払い義務がありません。
この事実を知らないドライバーは、本来益税として利益に組み込むことができる消費税をシレっと委託業者に取られています。



信頼できる業者を見分ける良い判断材料になるね!!
また、納税義務判定には「基準期間」と「特定期間」というものがあります。
基準期間は1/1~12/31の一年間を指し、特定期間は1/1~6/31の半年間を指します。
特定期間内であれば、本来「売上」を基準にするものを「給与等支払額」を基準に判定することができます。
例えば、半年で1100万円の売り上げてしまっても、給与等支払額が900万円なら課税対象にはならないということです。
このような「短期事業年度」を利用することで、節税を図ることもできるので、うまく活用しましょう!!
※現在はインボイス制度が始まっています、インボイス取得しなければクライアントから仕事を受けづらくなるので売上1000万円に満たない事業者でも消費税を支払わなければ仕事を受けることが難しくなっています。現状は経過措置として「2割特例」と言われる消費税を減額できる制度が用意されていますが、今後なくなります。
❺個人事業税


個人の事業所得に対してかかる税金、8・11月の2回払いです。
原則として所得が290万円以下の事業主には課されません。
運送業の場合は、所得に対して5%の事業税を納税する必要があります。
❻軽自動車税


4ナンバーの小型貨物自動車は、年間の自動車税がたった5000円で済みます。
ただ、車検証の登録日から13年がたった車は経年車重課といって20%の上乗せが課せられることも念頭に置いておきましょう。



めちゃくちゃ安いよね、普通自動車と比べると…震
❼自動車重量税


軽自動車の場合は、重量に関係なく一律3300円の税金がかかります。
タイミングは車検の際なので、そこまで意識する必要はありません。
13年以降は4100円、18年以降は4400円、経年車となれば割り増し料金が発生してきます。
おわりに… 税金カレンダー作りました笑


個人事業主になると「税金を払うために生きている錯覚」に陥ります…笑
資金をプールして、支払いに困らないようにしておきたいものですよね!!
国民年金、国民健康保険は説明するまでもないと思いますので省きましたが、カレンダーには記載しています。
軽貨物ドライバーが払うべき税金カレンダーを作りましたので、参考までに!!
税金カレンダー
| 1月 住民税4期、国民健康保険8期、国民年金9期 |
| 2月 国民健康保険9期、国民年金10期 |
| 3月 消費税、所得税(復興特別税が含まれます)、国民健康保険10期、国民年金11期 |
| 4月 国民年金12期 |
| 5月 自動車税、自動車重量税、国民年金1期 |
| 6月 住民税1期(復興特別税が含まれます)、国民健康保険1期、国民年金2期 |
| 7月 国民健康保険2期、国民年金3期 |
| 8月 住民税2期、個人事業税1期、国民健康保険3期、国民年金4期 |
| 9月 国民健康保険4期、国民年金5期 |
| 10月 住民税3期、国民健康保険5期、国民年金6期 |
| 11月 個人事業税2期、国民健康保険6期、国民年金7期 |
| 12月 国民健康保険7期、国民年金8期 |
個人事業主になると税金の全貌が見えてきます。
節税の意識がなければ所得の6割近く持って行かれることも…笑
軽貨物ドライバーは個人事業主です。
軽貨物運送業は経費が比較的少なく、利益を確保しやすい職種ですので、自分の利益は自分で守るスタンスで、税金とうまく付き合っていきましょう(^^)






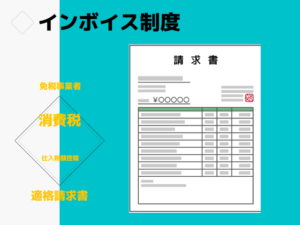
コメント